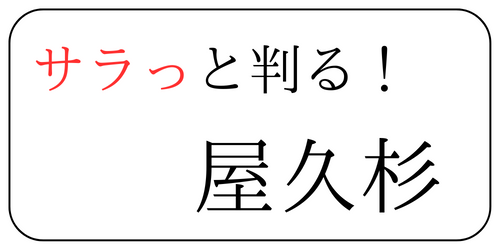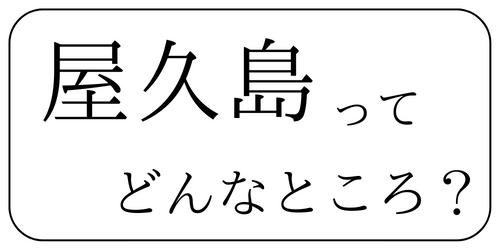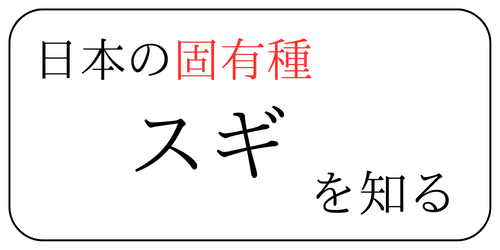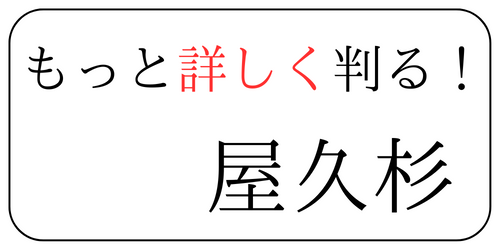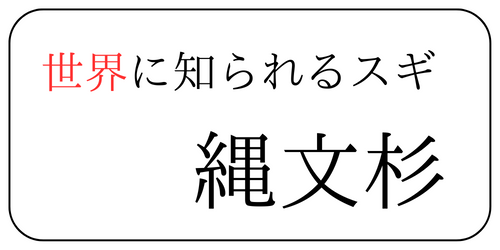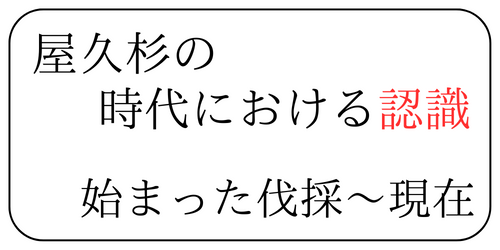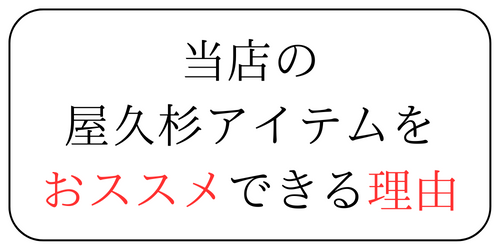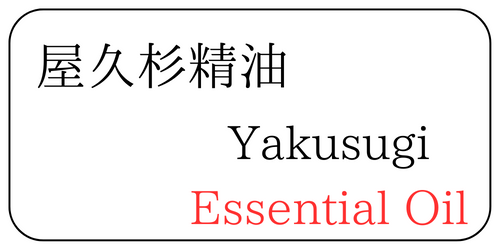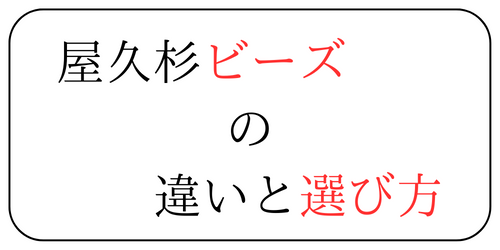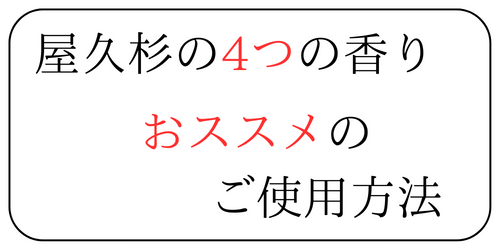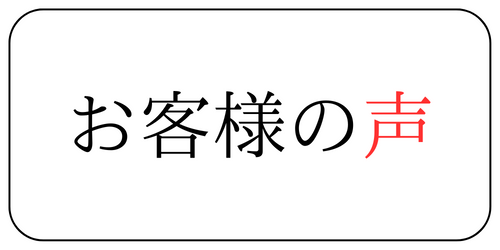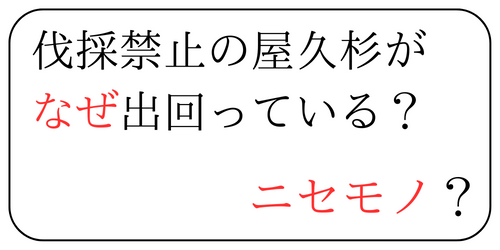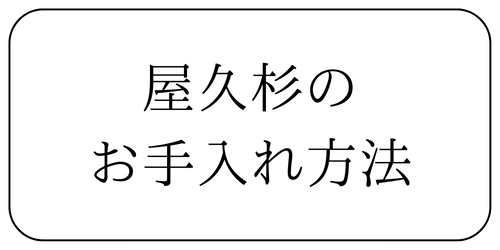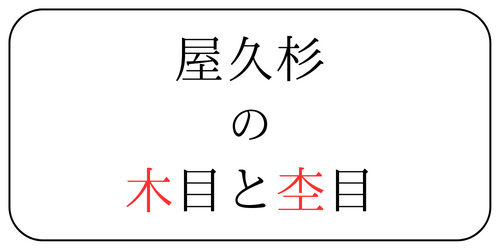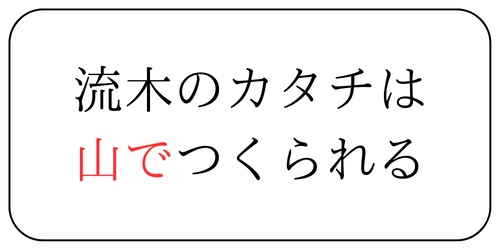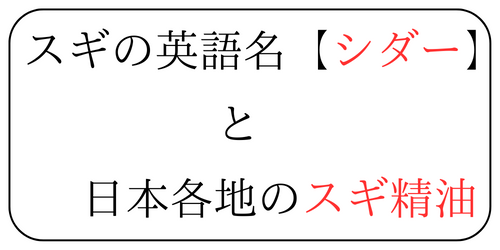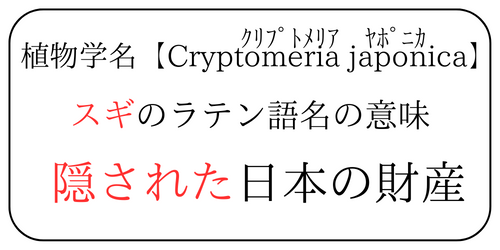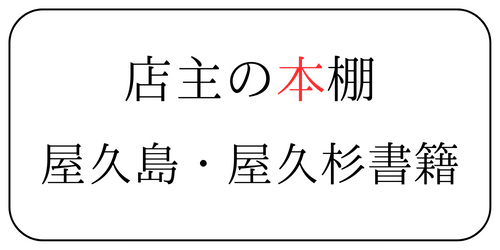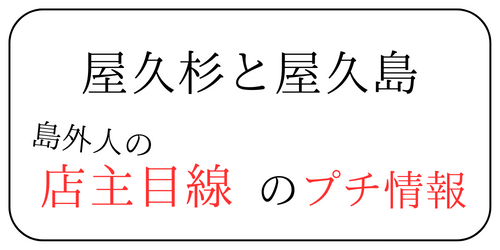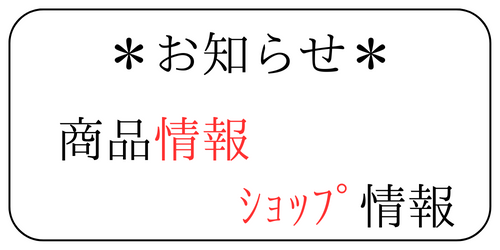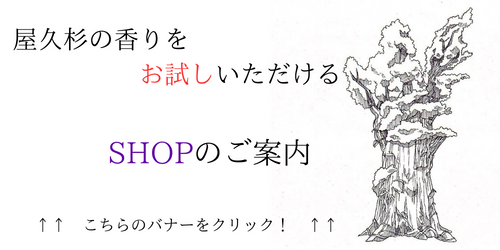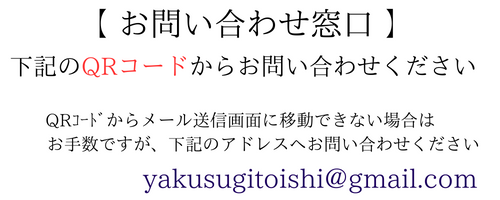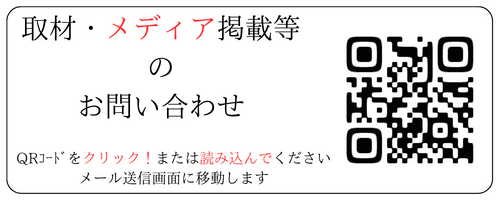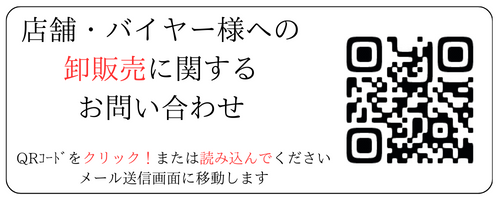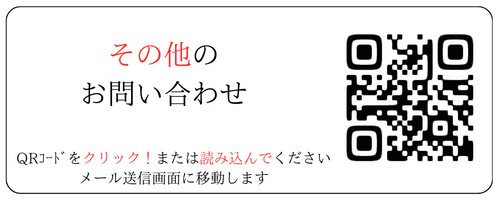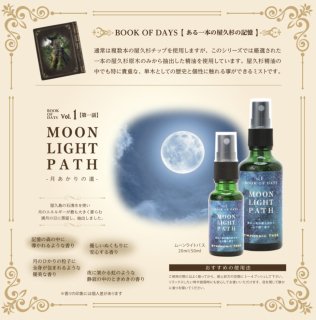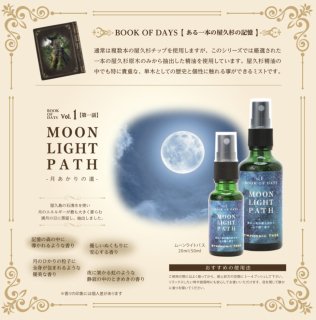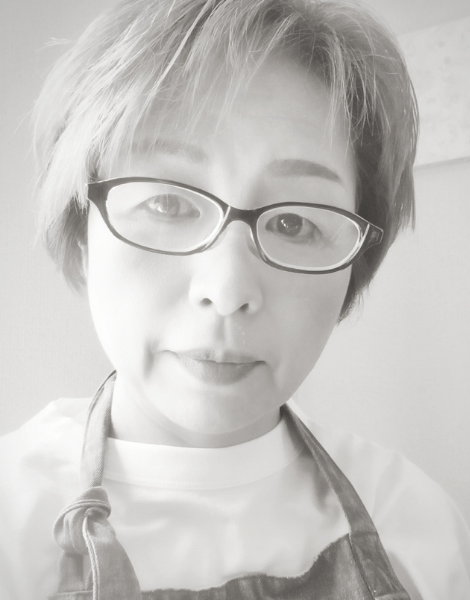屋久島ってどんなところ?

鹿児島県の離島 鹿児島県熊毛郡屋久島町
鹿児島県本土から南方に約60km離れた東シナ海に浮かぶ島
山、森、川、海と豊かな自然に恵まれた美しい島は
「洋上のアルプス[1]」「水の島[2]」「森の島[3]」などと呼ばれることもあります
面積 約505平方km 日本の島の大きさランキング 8位 (本土5島を除く)
円形に近い五角形をし、すり鉢を伏せたような島で淡路島よりやや小さい
周囲 約132km
外周部の道路を車で走ると2〜3時間で一周できる大きさ
島の約4割が屋久島国立公園に指定され、また島の約2割がユネスコの世界自然遺産に登録されています。
[1] 九州最高峰の宮之浦岳(1936m)をはじめ1000m以上の山が45座以上
連なる山岳島の景観から「洋上のアルプス」と呼ばれます
[2] 屋久島は雨が大変多く、「屋久島は月のうち、35日は雨という位でございますからね」と林芙美子の小説「浮雲」に書かれるほど。
年間平均降水量は平地で約4500?と東京の2〜3倍、山間部では約10000?となり、豊富な水が豊かな自然を作り上げていることから「水の島」と呼ばれます。
[3] 島の約9割が森林であることから「森の島」と呼ばれます。

・・・・・・ 屋久島の成り立ち 〜 弥生時代 ・・・・・・
1550万年前に地中深くでマグマが固まってできた花崗岩が4000万年前に作られた堆積岩を突き上げて隆起しはじめ、1400万年前に現在の屋久島の土台が出来上がりました。
その当時、それは陸地の一部で、離れたり、くっついたりを繰り返していたのが分かっており、2万年前は屋久島、種子島、九州本土は陸続きでした。
そして氷河時代が終わると地球温暖化の為に海水面が上昇し、洪積世から沖積世に移る頃には屋久島は現在に近い形となっていたと推定されています。
屋久島に人が住むようになった年代は定かではありませんが、
1万3000年前(旧石器時代)の阿姑ヶ山(あこがやま)遺跡からは屋久島産の水晶で作られた三稜尖頭器という槍などの先端に付ける鋭い刃物が出土されました。
7300年前には屋久島の北40kmの海底にある鬼界カルデラの大噴火があり、多大な被害を生み出す火砕流は屋久島、種子島、九州南部まで達し、生態系も縄文社会も壊滅させたと考えられています。[*]
そして、その後自然が再生されるまでには数百年〜1000年もの期間を要したとされ、その間の屋久島は無人の時代が続いたと言われています。
鬼界カルデラ噴火後に再び屋久島で人々の暮らしが確認できたのは、6000年前(縄文時代前期)です。
一湊松山遺跡では、轟式土器、曽畑式土器が出土されました。
4000年前(縄文時代後期)の横峯遺跡では西日本有数の竪穴住居群跡発見
2200年前(弥生時代中期)の火之上山遺跡では入来式土器、山ノ口式土器出土
[*]この火砕流は幸屋(こうや)火砕流と呼ばれ、噴煙柱は高度数十kmにも達し、屋久島においては特に北西〜北部を直撃したと推定されています。
当時の地層から炭化した樹木の破片が見つかり、森林の大部分は高温の為に焼けてしまったと想像されます。
しかしながら、南部の尾野間周辺地域の地層からは火砕流の堆積物が見つからなかった為、火砕流の直撃の被害を受けなかった地域もあったと考えられています。
※鬼界カルデラの大噴火時期を6300年前とする説もある。
(放射性炭素年代測定で暦年補正が施されたかどうかで年代値が異なるとのこと。暦年補正前6300年前、暦年補正後7300年前。最近では暦年補正後の年代が実年代に近いということがわかり、こちらでは7300年前としております。)
・・・・・・ 屋久島の気候 ・・・・・・

海では熱帯魚が泳ぎ、里ではガジュマルが育ち、ブーゲンビリアの花が咲く亜熱帯の気候から、九州最高峰が連なる高い山々の頂付近は2〜4mの積雪がある亜寒帯に近い気候となります[1]。
海岸線から山頂までの高さ約2000mに日本の南から北までの植物の移り変わる植生の垂直分布が見られることで植物の「日本の縮図」を見ることができます。
[1]最高峰の山々の頂の気候はだいたい旭川辺りの気候と言われています。
・・・・・・ 屋久島の特徴的な気象 ・・・・・・
多量の雨が特徴の屋久島の年間降水量は日本一です。
年間平均降水量 平地で約4500?(東京の2〜3倍)、山間部では約10000?
多雨の理由は海上に孤立した島の立地と形状にあります。
屋久島は赤道付近で温められた海流が北上する黒潮の海に囲まれています。
海上から吹く風は暖められた湿った空気で水蒸気を蓄えて、そびえ立つ山々の斜面を駆け上る為、上昇気流が起こり、上空に雲霧が発生することで、多雨の条件を作り出しています。
また、屋久島は台風の通過ルートと重なることも多く、進路を変える転向点になることも多い為に、風雨が長く続きやすくなり、雨量が多くなります。
春は梅雨、夏は台風、秋は秋雨前線、冬は北西季節風、更に一年中雨が降りやすい環境の屋久島は、豊富な雨量によって豊かな自然が守られ、育まれています。[*] [**]

[*]島全体で大小140もの川があり、至る所で水が湧き出ています。
水は島全体を潤し育て、屋久島の海をも育みます。
豊富な水は水力発電に活用され、ほぼ自然のエネルギーだけで島の電力を賄うことができており、孤島という環境の人々の生活は恵まれた水によって大きく支えられています。

[**]花崗岩が隆起してできた屋久島は降った雨が地下に浸透することなく岩肌を流れていきます。
その為にミネラルの含有が極めて少ない「硬度0」の超軟水となります。
川に流れつくその水は養分が少ない為に、水がとてもきれいです。
しかしながら養分が少ない為に川の魚はとても少ないのです

・・・・・・ 古からの山岳信仰 ・・・・・・・
海岸部に近い里から見られる山は前岳と呼び、島の中央にある里から見ることができない山を奥岳と呼んでいます。[1]
人々は、前岳は里を守り、自然の恵みを与えてくれる身近な山であると感じています。
それに対して里から遠く、ただただ深い山である奥岳のことは畏怖・畏敬の念を抱き、気軽に足を踏み入れてはいけない神が住まう神聖な領域であると山そのものを崇拝の対象としていました。[2]
1488年(室町時代)、法華宗布教の為に屋久島にやってきた日増上人は岳に登り、「南無妙法蓮華経」の神札を納めることで、屋久島の山岳信仰と法華宗という異教の融合を図りました。
神道の山の神である「山幸彦〈天津彦彦火火出見尊〉」を仏教の菩薩の姿である「一品法壽大権現」として祀り、屋久島の主護神としました。
このように古から続く山岳信仰と仏教が融合し、神仏習合となりました。
その頃に始まったとされるのが岳参りです。
24ある集落の岳参りのしきたりは集落毎に異なるものの、集落の代表者がそれぞれの集落の奥岳に祀られる一品法壽大権現に海と里の恵みを捧げ、集落の繁栄、豊漁豊作や家内安全などを祈るものでした。
一品法壽大権現を祀る祠、石塔の刻字は江戸時代のものが多く、その頃に盛んになったものと考えられます。
岳参りの神事が終わり、下山時には山の精霊が宿るとされるヤクシマシャクナゲの蕾のついた枝を持ち帰ります。[3]
持ち帰ったシャクナゲは帰りを待つ者へ山からの土産として配り、里や家の神様に供えます。
戦後〜高度成長期にかけては岳参りが途絶えていた集落が多くありましたが、世界自然遺産登録以降は復活させる集落が増えてきました。
現代の状況に合わせて簡略化したりしていますが、今では多くの集落がそれぞれのしきたりで岳参りを行っています。
※屋久島の山岳信仰がいつ頃から始まったのかは分かっていません。
推測の域を出ませんが、7世紀頃に九州で古代山岳信仰が形成されつつあり、九州一の高山が連なる屋久島の山岳信仰もこの頃には成立されていたとみてよいだろうと言われています。

[1]奥岳である永田岳だけは唯一里から見ることができます。
[2]かつて奥岳は女人禁制とされていました。
[3]国有林エリアにある為、普段は持ち帰ることはできませんが岳参りの時だけは許されています。
・・・・・・ 日本で初めての世界自然遺産登録 ・・・・・・

日本の固有種であるスギが樹齢数千年以上にも育つ優れたスギの生育地であること。
世界最大級の照葉樹林が広範囲にわたって原生状態にあること。
亜熱帯から亜寒帯に近い気候を持つ1つの島で、東アジアの南から北への植生の垂直分布が見られること。
これらの稀有な美しい自然環境が評価され、1993年、島全体の約2割のエリア[1]が青森県・秋田県にまたがる白神山地とともに日本で最初の世界自然遺産として登録されました。
[1] 世界自然遺産登録地は島全体の面積の21%のエリアで、原生自然環境保全区域、国立公園特別保護区及び第一種特別地域にほぼ重なっています。
・・・・・・ 屋久島へのアクセス ・・・・・・ 2023年10月時点
飛行機 鹿児島空港から35分 福岡空港から1時間5分
大阪伊丹空港から1時間40分

高速船 鹿児島本港から 直行便で約2時間

フェリー 鹿児島本港から 直行便で約4時間


鹿児島県の離島 鹿児島県熊毛郡屋久島町
鹿児島県本土から南方に約60km離れた東シナ海に浮かぶ島
山、森、川、海と豊かな自然に恵まれた美しい島は
「洋上のアルプス[1]」「水の島[2]」「森の島[3]」などと呼ばれることもあります
面積 約505平方km 日本の島の大きさランキング 8位 (本土5島を除く)
円形に近い五角形をし、すり鉢を伏せたような島で淡路島よりやや小さい
周囲 約132km
外周部の道路を車で走ると2〜3時間で一周できる大きさ
島の約4割が屋久島国立公園に指定され、また島の約2割がユネスコの世界自然遺産に登録されています。
[1] 九州最高峰の宮之浦岳(1936m)をはじめ1000m以上の山が45座以上
連なる山岳島の景観から「洋上のアルプス」と呼ばれます
[2] 屋久島は雨が大変多く、「屋久島は月のうち、35日は雨という位でございますからね」と林芙美子の小説「浮雲」に書かれるほど。
年間平均降水量は平地で約4500?と東京の2〜3倍、山間部では約10000?となり、豊富な水が豊かな自然を作り上げていることから「水の島」と呼ばれます。
[3] 島の約9割が森林であることから「森の島」と呼ばれます。

・・・・・・ 屋久島の成り立ち 〜 弥生時代 ・・・・・・
1550万年前に地中深くでマグマが固まってできた花崗岩が4000万年前に作られた堆積岩を突き上げて隆起しはじめ、1400万年前に現在の屋久島の土台が出来上がりました。
その当時、それは陸地の一部で、離れたり、くっついたりを繰り返していたのが分かっており、2万年前は屋久島、種子島、九州本土は陸続きでした。
そして氷河時代が終わると地球温暖化の為に海水面が上昇し、洪積世から沖積世に移る頃には屋久島は現在に近い形となっていたと推定されています。
屋久島に人が住むようになった年代は定かではありませんが、
1万3000年前(旧石器時代)の阿姑ヶ山(あこがやま)遺跡からは屋久島産の水晶で作られた三稜尖頭器という槍などの先端に付ける鋭い刃物が出土されました。
7300年前には屋久島の北40kmの海底にある鬼界カルデラの大噴火があり、多大な被害を生み出す火砕流は屋久島、種子島、九州南部まで達し、生態系も縄文社会も壊滅させたと考えられています。[*]
そして、その後自然が再生されるまでには数百年〜1000年もの期間を要したとされ、その間の屋久島は無人の時代が続いたと言われています。
鬼界カルデラ噴火後に再び屋久島で人々の暮らしが確認できたのは、6000年前(縄文時代前期)です。
一湊松山遺跡では、轟式土器、曽畑式土器が出土されました。
4000年前(縄文時代後期)の横峯遺跡では西日本有数の竪穴住居群跡発見
2200年前(弥生時代中期)の火之上山遺跡では入来式土器、山ノ口式土器出土
[*]この火砕流は幸屋(こうや)火砕流と呼ばれ、噴煙柱は高度数十kmにも達し、屋久島においては特に北西〜北部を直撃したと推定されています。
当時の地層から炭化した樹木の破片が見つかり、森林の大部分は高温の為に焼けてしまったと想像されます。
しかしながら、南部の尾野間周辺地域の地層からは火砕流の堆積物が見つからなかった為、火砕流の直撃の被害を受けなかった地域もあったと考えられています。
※鬼界カルデラの大噴火時期を6300年前とする説もある。
(放射性炭素年代測定で暦年補正が施されたかどうかで年代値が異なるとのこと。暦年補正前6300年前、暦年補正後7300年前。最近では暦年補正後の年代が実年代に近いということがわかり、こちらでは7300年前としております。)
・・・・・・ 屋久島の気候 ・・・・・・

海では熱帯魚が泳ぎ、里ではガジュマルが育ち、ブーゲンビリアの花が咲く亜熱帯の気候から、九州最高峰が連なる高い山々の頂付近は2〜4mの積雪がある亜寒帯に近い気候となります[1]。
海岸線から山頂までの高さ約2000mに日本の南から北までの植物の移り変わる植生の垂直分布が見られることで植物の「日本の縮図」を見ることができます。
[1]最高峰の山々の頂の気候はだいたい旭川辺りの気候と言われています。
・・・・・・ 屋久島の特徴的な気象 ・・・・・・
多量の雨が特徴の屋久島の年間降水量は日本一です。
年間平均降水量 平地で約4500?(東京の2〜3倍)、山間部では約10000?
多雨の理由は海上に孤立した島の立地と形状にあります。
屋久島は赤道付近で温められた海流が北上する黒潮の海に囲まれています。
海上から吹く風は暖められた湿った空気で水蒸気を蓄えて、そびえ立つ山々の斜面を駆け上る為、上昇気流が起こり、上空に雲霧が発生することで、多雨の条件を作り出しています。
また、屋久島は台風の通過ルートと重なることも多く、進路を変える転向点になることも多い為に、風雨が長く続きやすくなり、雨量が多くなります。
春は梅雨、夏は台風、秋は秋雨前線、冬は北西季節風、更に一年中雨が降りやすい環境の屋久島は、豊富な雨量によって豊かな自然が守られ、育まれています。[*] [**]

[*]島全体で大小140もの川があり、至る所で水が湧き出ています。
水は島全体を潤し育て、屋久島の海をも育みます。
豊富な水は水力発電に活用され、ほぼ自然のエネルギーだけで島の電力を賄うことができており、孤島という環境の人々の生活は恵まれた水によって大きく支えられています。

[**]花崗岩が隆起してできた屋久島は降った雨が地下に浸透することなく岩肌を流れていきます。
その為にミネラルの含有が極めて少ない「硬度0」の超軟水となります。
川に流れつくその水は養分が少ない為に、水がとてもきれいです。
しかしながら養分が少ない為に川の魚はとても少ないのです

・・・・・・ 古からの山岳信仰 ・・・・・・・
海岸部に近い里から見られる山は前岳と呼び、島の中央にある里から見ることができない山を奥岳と呼んでいます。[1]
人々は、前岳は里を守り、自然の恵みを与えてくれる身近な山であると感じています。
それに対して里から遠く、ただただ深い山である奥岳のことは畏怖・畏敬の念を抱き、気軽に足を踏み入れてはいけない神が住まう神聖な領域であると山そのものを崇拝の対象としていました。[2]
1488年(室町時代)、法華宗布教の為に屋久島にやってきた日増上人は岳に登り、「南無妙法蓮華経」の神札を納めることで、屋久島の山岳信仰と法華宗という異教の融合を図りました。
神道の山の神である「山幸彦〈天津彦彦火火出見尊〉」を仏教の菩薩の姿である「一品法壽大権現」として祀り、屋久島の主護神としました。
このように古から続く山岳信仰と仏教が融合し、神仏習合となりました。
その頃に始まったとされるのが岳参りです。
24ある集落の岳参りのしきたりは集落毎に異なるものの、集落の代表者がそれぞれの集落の奥岳に祀られる一品法壽大権現に海と里の恵みを捧げ、集落の繁栄、豊漁豊作や家内安全などを祈るものでした。
一品法壽大権現を祀る祠、石塔の刻字は江戸時代のものが多く、その頃に盛んになったものと考えられます。
岳参りの神事が終わり、下山時には山の精霊が宿るとされるヤクシマシャクナゲの蕾のついた枝を持ち帰ります。[3]
持ち帰ったシャクナゲは帰りを待つ者へ山からの土産として配り、里や家の神様に供えます。
戦後〜高度成長期にかけては岳参りが途絶えていた集落が多くありましたが、世界自然遺産登録以降は復活させる集落が増えてきました。
現代の状況に合わせて簡略化したりしていますが、今では多くの集落がそれぞれのしきたりで岳参りを行っています。
※屋久島の山岳信仰がいつ頃から始まったのかは分かっていません。
推測の域を出ませんが、7世紀頃に九州で古代山岳信仰が形成されつつあり、九州一の高山が連なる屋久島の山岳信仰もこの頃には成立されていたとみてよいだろうと言われています。

[1]奥岳である永田岳だけは唯一里から見ることができます。
[2]かつて奥岳は女人禁制とされていました。
[3]国有林エリアにある為、普段は持ち帰ることはできませんが岳参りの時だけは許されています。
・・・・・・ 日本で初めての世界自然遺産登録 ・・・・・・

日本の固有種であるスギが樹齢数千年以上にも育つ優れたスギの生育地であること。
世界最大級の照葉樹林が広範囲にわたって原生状態にあること。
亜熱帯から亜寒帯に近い気候を持つ1つの島で、東アジアの南から北への植生の垂直分布が見られること。
これらの稀有な美しい自然環境が評価され、1993年、島全体の約2割のエリア[1]が青森県・秋田県にまたがる白神山地とともに日本で最初の世界自然遺産として登録されました。
[1] 世界自然遺産登録地は島全体の面積の21%のエリアで、原生自然環境保全区域、国立公園特別保護区及び第一種特別地域にほぼ重なっています。
・・・・・・ 屋久島へのアクセス ・・・・・・ 2023年10月時点
飛行機 鹿児島空港から35分 福岡空港から1時間5分
大阪伊丹空港から1時間40分

高速船 鹿児島本港から 直行便で約2時間

フェリー 鹿児島本港から 直行便で約4時間